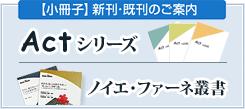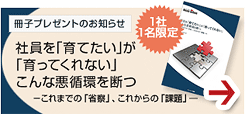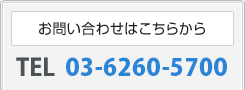人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年10月20日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-16-部下指導に必要な管理職の“学びほぐし”
職場でよく見られる光景の一つに、上司の「わかったか?」という問いかけに、部下が「はい、わかりました」と答える場面がある。形式としては成立しているが、このやり取りが本当の理解や成長につながることは少ない。多くの部下は、上司に対して「わかりません」とは言いづらく、たとえ理解が曖昧でも「はい」と返すしかないのが実情だ。
ところが、上司の側はその言葉に安堵し、指導を終えた気になってしまう。こうしたやり取りの積み重ねが、部下の成長を妨げ、組織全体の停滞を招く要因となる。部下指導において重要なのは、言葉の表面ではなく、部下の理解の深さを確かめ、行動に結びつけるための対話である。そのためには、上司自身の問いかけ方や考え方を見直す必要がある。
重要なことは、部下に「わからないことは当然だ」と感じさせる安心感を与えることである。質問を歓迎する姿勢を示し、理解できないことを恥ずかしいと思わせない環境を作る。上司の何気ない一言が、部下の心を閉ざすこともあれば、開くきっかけになることもある。次に、理解度を問うのではなく、行動に焦点を当てた質問をすることが有効だ。たとえば「次に何をすればいいと思う?」「何か問題があったらどう対処する?」といった具体的な問いかけによって、部下の理解の程度や思考プロセスが自然と明らかになる。さらに、「どこが難しそう?」「実行するとしたらどこがネックになりそう?」と尋ねることで、抽象的な「わからない」を具体的な課題に変えることができる。これは上司が部下の思考を引き出すための重要なステップである。
説明して終わりにするのではなく、実行とフィードバックのループを作ることが不可欠だ。「やってみてどうだった?」という振り返りを通じて、部下のつまずきを可視化し、次の成長につなげる。さらに「もし○○だったら、どうする?」と仮説的な質問を投げかけることで、応用力や本質的な理解を促すことができる。こうした対話の積み重ねが、部下の主体的な学びを支える。つまり、「問い」をデザインすることである。
部下の成長を支えるためには、上司自身の姿勢が問われる。特に変化の激しい現代において、過去の成功体験や慣れ親しんだ指導方法が必ずしも通用するとは限らない。ここで重要になるのが「学びほぐし(アンラーニング)」の考え方である。学びほぐしとは、過去に身につけた知識や思考の枠組みを一度解きほぐし、新しい視点や方法を取り入れるプロセスを指す。管理職は長年の経験を通じて形成された固定観念に縛られやすい。しかし、それこそが変化への対応を妨げる壁となる。
自らの経験や知識が時代遅れになっているかもしれないと認識し、柔軟に学び直す姿勢を持つことが求められる。
学びほぐしを実践するためには、意図的に新しい環境に身を置くことが有効だ。異業種の人との交流、これまで関心のなかった分野への挑戦、社外のセミナー参加などを通じて、自分の思考の枠を広げる。また、部下の声に耳を傾ける「下問の姿勢」も重要である。現場で働く若い世代の意見には、しばしば新しい発想や気づきが含まれている。上司がそれを受け止めることで、組織全体の学びが活性化する。
管理職にとって「教えること」は重要だが、それ以上に「共に学ぶこと」が求められる時代になっている。部下に自律的な思考と行動を促すためには、上司自身が学びを止めず、柔軟に変化し続ける姿勢を示すことが最大の指導となる。失敗を恐れずに新しいやり方を試し、そこから学ぶ姿を見せることこそ、部下にとって最も説得力のあるリーダーシップの形である。「わかりました」という言葉の裏に潜む沈黙を見逃さず、部下の理解を丁寧に掘り下げる。その過程で、上司自身の思考の枠をも見直し、学び直していく――この双方向の成長サイクルが、これからの組織に不可欠な「学習する職場」を生み出す。
部下指導の本質は、教え込むことではなく、考える力を引き出すことにある。そしてそのためには、管理職自身が“学びほぐし”を通じて、固定観念を手放し、柔軟に学び続ける存在でなければならない。部下の「わかりました」を本物の理解に変える第一歩は、上司の学びを“ほぐす”ことから始まる。
| 一覧へ |
![]()