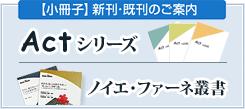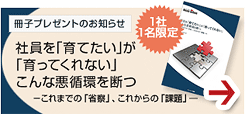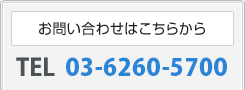人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年10月27日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-17-部下に信頼されない管理職の行動
どのような立派な経営理念を掲げても、現場で部下の信頼を得られない管理職のもとでは、組織は動かない。企業が持続的に成長するためには、戦略の巧拙以前に、管理職が部下から「この人となら成果を出せる」と思われることが前提となる。だが現実には、信頼を得られず「頼りにならない上司」と見なされるマネージャーが少なくない。
彼らの行動には明確な共通点がある。それは、情報、企画、上層との交渉、公平な評価―この4つの要素を正しく扱う能力の欠如である。上司とは命令する存在ではなく、情報と人をつなぎ、組織知を循環させる“媒介者”でなければならない。この認識の欠落こそ、信頼を損ねる根本原因である。
最も基本的な欠陥が情報伝達能力の欠如だ。経営戦略や新技術、顧客動向、競合情報など、会社からマネージャー層に届く情報は膨大である。信頼される上司は、その中から部署や個々のメンバーにとって重要な要素を選び出し、意図をもって共有する。どの情報を、誰に、どのタイミングで伝えるか―そこに上司の力量が現れる。一方で頼りにならない上司は、受け取った情報をそのまま全員に転送するか、あるいは放置する。結果として、情報の優先順位が不明確となり、現場の判断は鈍化する。情報は“伝える”ことでなく、“編集して届ける”ことで価値を生む。これを理解していない 上司は、組織の流れを止める存在となる。
次に問題となるのが、企画推進の方法論の欠如である。新しい企画を社内でどう動かすかという実践知を持つ上司は意外に少ない。優れたマネージャーは、小さな成功事例を基点に成果を拡張する。つまり、「小さな成果→期待感→より大きな成果→さらなる期待感」という雪だるま式の循環を生み出し、組織に波及効果をもたらす。しかし頼りにならない上司は、価値の芽を見つけても、仮説構築や資源調達、成果共有といったプロセスを描けない。結果、部下の挑戦は単発で終わり、再現性のある成果にはつながらない。部下が「この上司のもとでは成長できない」と感じる瞬間である。
目標達成に必要な予算やルールを獲得するためには、上層部に意見を届け、合意を形成する力が欠かせない。優れた上司は、全体最適の観点から自部署の要望を整理し、説得力ある論理で上層部を動かす。だが頼りにならない上司は、上層部に顔も覚えられず、発言が軽視される。結果、部下は「自分で直接プレゼンしたほうが通る」と感じ、指揮命令系統が形骸化する。
ガバナンスを支えるのは上司の交渉力である。上通性を欠いた管理職が増えれば、現場は孤立し、組織は分断されていく。公平感の欠如が致命的な問題となる。上司に対する信頼を決定づけるのは、評価とフィードバックの妥当性だ。どの行動を評価し、どの成果を重視するのか。そこに上司の価値観が表れる。不透明で的外れな評価を下す上司は、「何も見えていない」と部下から見切られる。特に、見栄えの良い報告書や時代遅れの企画を高く評価し、実務的な成果を軽視するような姿勢は、信頼を瞬時に失わせる。アウトプットを正しく評価できない上司は、今の成果主義社会において存在意義を失いつつある。
部下に信頼されない上司とは、情報、企画、上層交渉、公平な評価―この4つの機能のいずれか、あるいはすべてを欠く人物である。逆に言えば、これらを意識的に磨くことが信頼構築の第一歩となる。情報を選び、意味づけて共有する。小さな成果を拡張し、組織の期待感を高める。上層部を説得して資源を獲得する。そして、努力と成果を正当に評価する。―この4点を実行する上司は、自然と部下からの信頼を得る。
信頼を得るとは、威厳を保つことではない。部下が「この上司なら自分の仕事を理解してくれる」と感じる状態をつくることだ。マネジメントとは、支配ではなく信頼の設計である。頼りにならない上司は組織のボトルネックとなるが、信頼される上司は組織の潤滑油となる。どちらの存在になるかは、日々の行動次第だ。
| 一覧へ |
![]()