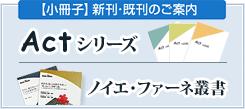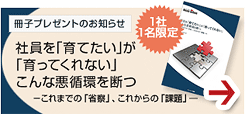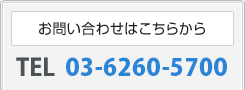人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年10月06日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-15-現場マネジメントに不可欠な部下評価の要諦
人事マネジメントとは、企業の経営資源のうち「ヒト=人材」をどう活かすかに焦点を当てた営みである。採用や育成、配置や評価といった仕組みを通じて、人と組織の力を最大化することが目的だ。しかし、その実践の中心にいるのは管理部門ではなく、現場の管理職である。現場が動かなければ人事マネジメントは機能しない。それにもかかわらず、いつのまにか「人事のことは人事部がやるものだ」と思い込んでしまってはいないだろうか。
現場で起きた人の問題に対し、法制度の理解や労務知識を欠いたまま初動を誤る例は少なくない。結果として、管理部門が火消しに追われ、現場は信頼を失う。人事マネジメントは制度の問題ではなく、現場の責任の問題だという原点を、今いちど自問する必要がある。私たちは経営戦略と人材戦略をどう結びつけているのか。部下を「人的資本」として活かすために、どのような働きかけをしているのか。現場の一つひとつの判断が、組織の将来を形づくっていることを、日々の中でどれだけ意識しているだろうか。
人を評価するという行為ほど、管理職の姿勢が試されるものはない。ある調査では「人事評価に満足している」と答えた社員はわずか2.8%だったという。評価される側の不満は、単に結果への不満ではなく、「どのように見られているのか分からない」「どうすれば評価されるのかが曖昧だ」という不安の表れでもある。
管理職は往々にして、評価基準を自分なりに理解しているつもりでいる。しかし、それは本当に部下と共有されているだろうか。成果を可視化するためにKPIやOKRを用いても、数字の背後にある努力や学習のプロセスを見落としてはいないか。短期的な成果だけを追い、部下の成長の芽を摘んでしまってはいないか。評価は部下を測る場であると同時に、自分のマネジメントを映す鏡でもある。そこに恣意性や思い込みが潜んでいないか、常に自問し続けることが求められる。
■評価姿勢を問い直す三つの視点
第一に、「公正さと一貫性」は本当に保てているだろうか。同じ基準で見ているつもりでも、日ごろの印象や感情が判断を左右していないか。評価の軸を明確にし、日常の中で一貫性を保つための工夫を怠っていないかを省みたい。
第二に、「プロセスレベルの目標設定と記録化」は形骸化していないだろうか。結果だけでなく、過程をどう評価するかを明確にしなければ、努力や挑戦を正当に扱うことはできない。期首の段階で部下とともに目標をドキュメント化し、何をどのように成長として認めるのかを共有しているだろうか。抽象的な「頑張り」ではなく、具体的な行動と学習の痕跡をどう捉えるかが、評価者の力量を決める。
第三に、「自己評価との対話」はできているだろうか。上司の視点だけで判断を下していないか。部下の自己認識に耳を傾け、そのズレを対話によって埋めようとする姿勢があるか。評価は一方的な宣告ではなく、相互理解を深める場である。自己評価を通じて部下が自らの課題を自覚するプロセスこそ、成長への出発点になる。
評価とは、点をつける作業ではなく、人を育てる営みである。そこに公正さや一貫性がなければ、評価は管理職自身の信頼をも失わせる。逆に、評価を通じて部下と真摯に向き合い、学びと成長の対話を重ねることで、組織の空気は確実に変わっていく。
管理職として、私たちは日々の判断の積み重ねの中で、組織の文化をつくっている。人をどう見るか、人の努力をどう扱うか、その姿勢がそのままマネジメントの質を決める。部下を評価する前に、自らの評価姿勢を問い直す。そこからしか、信頼に基づく人事マネジメントは始まらない。
| 一覧へ |
![]()