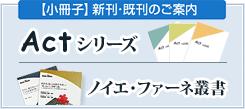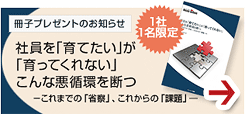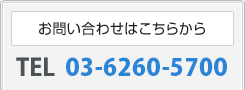人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年09月29日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-14-部下を支援するサジ加減を間違えない
日本企業の現場でマネジメントを担う管理職世代は、景気後退期に社会人生活をスタートさせた者が多い。この世代は「失われた〇〇年」の初期に就職したものの、高度経済成長期の雰囲気を色濃く残す上司や先輩のもとで育ってきた。仕事とプライベートの境界は曖昧で、上司からの急な指示にも厭わず従うことが「習い性」となり、職場では“察する文化”が重んじられた。
こうした風土は、経営と従業員、従業員同士の関係性を「家族的関係」と誤解させ、上司からの理不尽な要請に耐える文化や、非倫理的行為を容認する危うさを生み出してきた。とりわけ中小企業ではこの傾向が強く、経験値重視の風潮の中で、体系的なマネジメント教育や訓練を受けないまま現場を任される管理職が少なくない。つまり今日の管理職は、前世代の上司の下で「右往左往しながら生き残ってきた者」であり、必ずしもマネジメントの原理原則を十分に体得しているとは限らない。
一方、現在の若手社員は仕事の意味や手順について詳細な説明を求める傾向が強い。「失敗しても構わないからやってみろ」といった従来型の指導は、彼らには「放置されている」と受け取られかねない。言い換えるなら、彼らは仕事を理解し成長するために上司からの“助け舟”を必要としており、それを求めてもいるのである。
ところが、現場マネジメントを担う世代が支援を渋る態度を示した途端、若手は組織への距離感を深める。しかも今日の若手は、そうした疎外感を表立って示さない“強かさ”を持つため、日常業務の中から彼らの離反意識を察知することは難しい。管理職はこの現実を認識し、部下のモチベーションの変化を慎重に見極める必要がある。
「育たなかったのは、教えなかったからだ。育たなかったのは、教えたからだ」という言葉がある。これは教えることのサジ加減の難しさを端的に示している。教えなければ何も身につかないが、教えすぎても自分で考え行動する力は育たない。部下支援においても同じことがいえる。
支援が少なすぎれば成果は上がらず、多すぎれば依存心を助長する。タイミングも肝心で、早すぎる支援は過保護となり、遅すぎる支援は自信喪失や失敗につながる。管理職に求められるのは、この微妙なバランスを見極める力量である。単に“優しく教える”か“突き放す”かではなく、部下の状態や業務内容に応じて適切な距離感をとることが肝要だ。
具体的にどう支援すべきか。第一に、「初めから正解を示さず、答えを小出しに与える」ことである。肝心な部分まで上司が代わってやってしまえば、部下の思考力や判断力は育たない。第二に、「大きな障害はあらかじめ取り除く」ことだ。部下自身の力ではどうにもならない障害があっては、いくら試行錯誤させても育成にはつながらない。これは単に業務上の負荷軽減ではなく、上司の意地悪さに映らないよう配慮することでもある。部下にはなるべくギリギリまで自力で挑戦させ、最終的には達成感を得られるよう導くのが上手な支援だといえる。ただし現実の業務は成果や納期が伴うため、遅れや失敗が許されない場面も多い。そのため上司は、どこまで部下に任せるか、どこから介入するかを日々判断しなければならない。支援のサジ加減を見誤ることは、部下の自信喪失や組織への不信につながる。一方で、適切なサポートは部下の成長と組織全体の成果向上につながる。
管理職がまず意識すべきは、自身が属してきた旧来型の文化をそのまま部下に適用しないことだ。自らの経験値や成功体験だけに頼るのではなく、マネジメントの原理原則を学び直し、部下の特性や時代の変化を踏まえた柔軟な支援を実践することが求められる。支援とは“やってあげること”ではなく“育てること”である。そのためには、部下の自立を妨げない範囲で障害を取り除き、成功体験に導く。その積み重ねが組織への信頼感を醸成し、管理職自身のリーダーシップを強化する。「部下を支援するサジ加減を間違えない」とは、単なる技術論ではなく、上司自身が変化する覚悟のことでもある。自らのマネジメントを内省的に振り返り、適切な距離感をもって部下の成長を支えることが、管理職に求められる。
| 一覧へ |
![]()