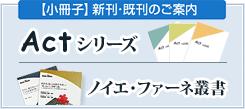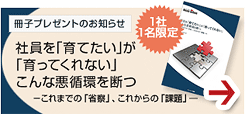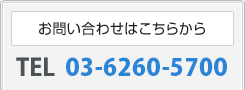人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年09月22日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-13-世代論に安易に流されない部下との関り方
職場において若手社員との関わり方を考えるとき、まず意識したいのは「世代論」に安易に流されない姿勢である。確かに日本社会には、バブル崩壊後の就職氷河期を経験したミレニアル前期世代、リーマンショック時期に就職活動を行ったミレニアル後期世代、さらには「ゆとり世代」や「Z世代」といった区分がある。しかし、それらの呼称やイメージはしばしば雑であり、個人の背景や価値観を一括りに説明するには限界がある。
「ゆとり世代」の期間が実質わずか6年しかなかった事実は、その象徴だといえる。そもそも日本の「Z世代」は、親世代の不況や社会不安を目の当たりにして育ち、お金に対してシビアで倹約的な傾向を持つとされるが、それもあくまで統計的傾向であり、個人を決めつけるものではない。従って、管理職や先輩社員が「最近の若手は〇〇だ」という先入観で部下を見てしまうこと自体が、現場の円滑なマネジメントを妨げる要因となる。
現場で実際に観察される若手社員の行動特性には一定の傾向があることも否めない。例えば、失敗や目立つことへの恐怖心、極端な平等志向、大人の評価軸を先読みして振る舞う慎重さ、自分から提案・決断することへの忌避、そして「やりたいこと」が不明瞭なため「自由にやってごらん」という助言を圧力と感じる傾向などである。また、100人のうちの1人に埋もれたいという意識、リスク回避志向、そして「わからない・できないことがあっても相談しないが、逆に丁寧な指導は求める」という相反する行動も見られる。
彼ら彼女らは自ら進捗を報告するより、上司が「どうなった?」と声をかけてくれるのを待つこともある。表面的には卒なく対応し、受け身ではいけないと理解しながらも、他者が正しいやり方を示してくれるまで慎重に動かない姿勢もある。「正解」がない事柄に不安を抱き、演繹的に物事を考える一方で、トライアンドエラーを苦手とする傾向も指摘されている。こうした特徴は、世代や教育制度だけでなく、社会環境の変化や企業文化、個々人の経験が複合的に影響して形成されたものだ。
ここで重要なのは、「だから最近の若手は駄目だ」「自分たちの頃はこうだった」と切り捨てるのではなく、上司世代自身が自らの思考習慣や指導スタイルを相対化することである。確かに、今日の若手社員は「プライベートが第一、仕事はその次」と映る価値観を持っているかもしれない。しかし一方で、かつての管理職世代も今では残業を減らし、定時退社や有給休暇取得を当然の権利として受け入れているはずである。子育て世代への配慮や働き方の柔軟化など、企業文化自体が変容してきた今、「最近の若手は…」「自分が新人の頃は…」という繰り言を繰り返しても何の解決にもならない。むしろ、上司自身が「これまでの自分たちの働き方・指導のあり方」を振り返り、必要に応じて軌道修正することこそが求められる。
どのように関わればよいのか。第一に、若手社員を「世代」というラベルで安易に括らず、一人ひとりの特性や状況を丁寧に観察することである。第二に、過度な放任や丸投げを避けつつ、段階的なガイドラインや具体的な目標を示し、安心して挑戦できる環境を整えることだ。第三に、彼らが「正解がないこと」に不安を感じる特性を踏まえ、試行錯誤の重要性や考え方のプロセスを具体例を交えて伝えることも有効である。最後に、ハラスメントを恐れて距離を置くのではなく、対話の質を高める努力を怠らないことである。
上司が「部下に媚びる」のではなく、「部下を理解したうえで適切に導く」姿勢を持つことが肝心だ。世代論に基づく安易なラベリングは、部下の行動や価値観を理解する近道ではなく、むしろ固定観念を強化し、柔軟な対応力を失わせる危険を孕んでいる。時代とともに価値観や働き方が変容することは避けられないが、組織において成果を生み出すために不可欠な信頼関係、丁寧な対話、そして誠実なマネジメントの重要性は不変だ。
管理職は、若手社員を単なる「世代」という抽象的な枠組みで捉えるのではなく、個々人の背景や特性を踏まえたうえで接し、その潜在力を引き出す責任を負っている。こうした取り組みを重ねることこそが、世代を超えて持続可能な組織文化を築き、将来にわたって活力ある職場を実現するための確かな基盤となる。
| 一覧へ |
![]()