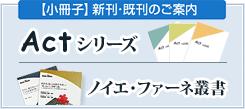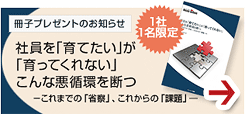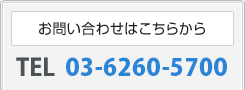人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年03月17日号
“残念な上司”になってはならない-4-ガバナンス視点に立って「年上部下」と接する
日本では年功序列や終身雇用制度の残滓により、基本的に「部下は年下である」というケースが多かった。しかし、近年は雇用の流動化が進み中途採用などで、これまで主流であった年功序列による上下関係が崩れはじめ「年下上司・年上部下」が徐々に目立ってきた。この傾向は定年後の65歳まで「再雇用義務化」によりますます強まってくる。
2023年に行われたある調査機関の調査によると、30〜50代会社員のうち、「直属の上司が年下」である人は約20%。従業員数2000人以上の大企業では、30%近くに達している。今後も高齢社員の増加などで「年下上司」が「年上部下」をマネジメントするケースが増してくる。
一方でマネジメントする側である「年下上司」は「年下部下」の指導経験を単純に「年上部下」に当てはめることはできないとの自覚がある。このため年齢が上だからこその遠慮や忖度が働き指示が曖昧になってしまうことが起こる。これは同期の間柄で職位の上下関係が発生する場合も同様である。
もちろん、部下とはいえ「年上部下」にはプライドがある。「年下上司」に教えられることに抵抗感を抱く者もいる。この種のセンシティブな関係性を意識しながら「年下上司」は、あくまでも「指示・命令」という組織性を堅持して「年上部下」のプライドを傷つけないように指導する必要がある。年齢に対する配慮をしつつ遠慮していては伝えるべきことが伝えられない。あくまでも上司の「指示・命令」は年齢に関係のない役割であるということを忘れてはならない。
自分が上司であるとはいえ、「年上部下」は人生の先輩ともいうべき存在である。このため、敬意を持って接する。決して呼び捨てやため口ではなく、敬語や丁寧語で話す。何気なく「年下部下」のように接することで反感を買われてしまう場合がある。積極的に「年上部下」の意見を求める。「年長者としての意見を聞きたい」などの言葉で信頼していることを伝えることで良好な関係性を築く端緒にもなる。同時に業務のヒントを得られる可能性があるだけではなく「年上部下」のモチベーション維持につながる。
上司と部下という立場は、あくまで会社組織から与えられた仕事上の関係である。上司の役割は部下の指導・育成である。会社組織の運営において相手が年上だからといって遠慮する必要はない。上司としての役割であると割り切って「年上部下」と接する必要がある。
「年上部下」と日頃からの何気ない会話が非常に重要である。仕事の場面に限らない「年下部下」に対する上司の側からの自己表出は信頼関係の構築にもなる。業務以外の会話で発せられる発言内容を通して互いに相手の価値基準などを把握しておくことなどが、円滑な指示や指導に役立つことになる。
「年上部下」に対して明確な指示を出す。気を使いすぎて不必要に言葉を選んだ分かりにくい指示や曖昧な表現は禁物である。これらの姿勢をもってしてもそれに応えない「年上部下」に対しては、職務を司る上司としての立場を前面にして「年下部下」への対応と変わらぬ毅然とした態度で臨む必要がある。さもなければ職場のガバナンスを維持することはできない。
| 一覧へ |
![]()