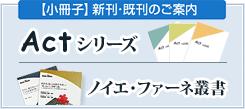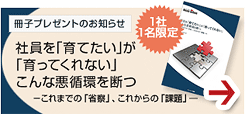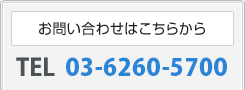人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年03月10日号
“残念な上司”になってはならない-3-判断の基準はあくまでも“行動変容”
一時期、部下の育成手法において「褒めて伸ばす」式の指導・育成手法が喧伝されたことがあった。しかし、実のところ「褒めることによる効果はあまり大きいわけではない」という研究もある。まして部下のご機嫌をとるために褒めても何の役にも立たない。無意味に部下を褒めたところで、賢く強かな部下からは体よくあしらわれるだけである。
何よりも最近の若手は人前で褒められることを極端に嫌うという傾向もある。この種の若手に対して上司が良かれと思って褒めたところで逆効果である。一昔も二昔も前にいわれていた「褒めるのはみんなの前で、怒るのは一対一で」などは今の時代に通用しない。まして、一対一で叱ったりするならば「密室でハラスメントを受けた」といわれかねない。
上司の側は自分が企業社会の中で育んできた経験などが、今日の部下に通用しないということを自覚しなければならない。上司の側が自分の経験値でしか部下に接することができない理由は極めて簡単である。それは上司の側が自らの経験を懐古的に捉えているからである。同時に自らの経験値を変更していくためには“学び直し”というコストがかかるからである。コストとは単に金銭的なものだけではなく、精神的なコストである。この種の上司に限って「せっかく教えているのに部下が理解していない」という愚痴を漏らすことになる。
しかし、こうした愚痴は上司の側が常に正解を持っているという幻想に取りつかれているようなものだ。より厄介で時として悪質なのは、部下の育ってきた時代背景を鑑みることなく上司の経験則を絶対化してしまうケースである。つまり、自らの企業人としての成長過程をノスタルジックに語る傾向に陥ることだ。この種の上司が部下から「それは貴方の時代だから通用したことではありませんか…」と問われたならば“ぐうの音も出ない”はずである。
褒める行為に関してもあくまでも職場での何気ない対話や雑談を含めた、上司と部下の間で“良好な関係性”が形成されていなければ、いくら上司が部下を褒めたところで部下から“何か裏があるのではないか”と勘ぐられて警戒されるのが関の山である。
そもそも部下は嫌いな上司や自分が評価していない上司から褒められても嬉しいと思わない。さらに上司と部下の“日常の関係性”が悪ければ、上司の褒め言葉も上滑りすることになる。つまり、無媒介で無意味な上司の褒め言葉などは、部下から上司の底の浅さを見抜かれ、逆に舐められるだけに終わることにもなる。
上司が部下を褒める目的はあくまでも「部下に期待する“行動”を繰り返してもらうため」であり、組織にとって好ましい行動を増やすためである。いくら一つ一つの行為を褒めたところで、それらが再現性のある行動として堅持されていなければ意味がない。人間の意識などは簡単に変わるものではない。部下に教え諭し「わかりましたと」と部下がいったところで、行動変容がなければ本当に「わかった」ことにはならない。
この意味で一つ一つの行動に対して出来ているか、出来ていないかという判断基準で接していく必要がある。好ましい行動が出来ていれば褒める。出来ていなければ怒るということである。この道理を理解しない上司は、部下が上司に対して「わかりました」としか返事が出来ない関係性をわかったうえ敢えて、部下に「わかりました」といわせることに満足感を覚える嗜虐性さえ疑われることになる。
| 一覧へ |
![]()