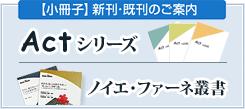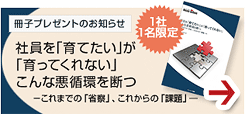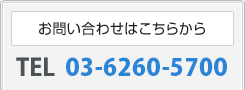人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年02月10日号
“残念な上司”になってはならない-2-部下から見て“残念な上司”の特長
◆一貫性がない
部下がビジネスリテラシーの力量が乏しく上席者として不適格と思う上司は、発言(口)と本心(腹)と行動(背)が一貫していない。この種の翔氏は言うことがコロコロ変わり、信念を持って本気で語っていないため、発言に自分の思いが込められていない。
これは真剣に物事を思考したうえでの「朝令暮改」とは意味が異なる。部下からするならば「どうせまた上の者の影響を受けてすぐに自分の発言を撤回するのだろうな…」と思ってしまい頼りにならない。一貫性のなさとは、仕事上では部下にとって「軽さ」と同意語でもある。
◆自分の利益を優先する
部下に対して「自分の思った通りにやってみろ…」と言っておきながら、いざ失敗した場合には部下やメンバーをかばうことなく、会社に対して平然と「ミスが起こらないように私は何時も注意喚起をしているのだが…」とおく目もなく自己保身と責任回避に走る。
部下の成果を露骨に横取りする等の上司の行動に対し、部下は公然と抗議することはしない。ただし、この種の上司に対して自分の立場しか考えない低次元な行為であると位置づける。そして、憐れみさえ感じ始める。この結果として部下は自然と「指示待ち」の優位性を感じるようになる。
◆肩書で人を動かそうとする
年功による経年や温情主義によって“ところてん式”に辛うじて昇進した実力のない上司ほど、自分を不必要に大きく見せたいという意識が強く働くものだ。現象としては自分に着いた肩書で部下を動かそうとする。そして端々に「自分の言うことを聞けないのか」式の発言をにじませながら、部下をコントロールしようとする行為に走る。
部下に対して明確で的確な説明をしながら納得を促していくのではなく、権威的・高圧的に部下を自分の駒として動かしたがる。要するに自分の力量で部下を動かすことができないが故に権威的な肩書に頼るしかない。権威は自らの働きによってついてくるものであるということが理解できない。この種の上司に対して部下は「実力が備わっていない」と見抜き、適当にあしらい蔑むものである。
◆向上心がない
一定の役職に就いていることに満足し、さらに上を志向しない上司は部下から見たならば努力を怠っていると見なすものだ。この種の上司は結局のところ視座が低く視野も狭いものである。部下から見たならば向上心のない上司に映る。
経営環境の不確実性が増す中で部下は、上司に戦略的な構想力を求めるものである。戦略的な構想力を持たない上司は、結果的に多様な意見を統合することなどできない。こうした道理は部下が一番感じるものである。何時までも一人のプレイヤーとしての意識にとどまって、経営的な視点・姿勢を持てない上司を部下は決して自分のロールモデルにはしない。
| 一覧へ |
![]()