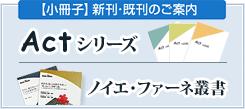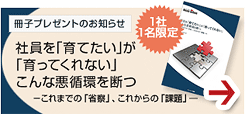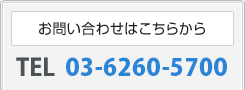人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年02月03日号
“残念な上司”になってはならない-1-部下にとって頼りにならない上司
部下が新しい価値の可能性を見つけて提案してきた場合に、上司はその部下からの提案を精査し、「自部署として推進する」と判断をしたならば、その実現に向け資源を獲得する力、適切な目標設定する力、成功を周りに宣伝する力、上層部からの期待の獲得する力などの「力」=パワーの総動員が必要となる。当然のことながら部下は最初からそれらの「力」を持っている訳ではない。
上司にこの種の「力」がなければ部下からのせっかくの価値ある提案はお蔵入りとなる。こうした事態に陥ったならば、部下は“せっかくチャンスがありながら、上司の力量不足が原因で新しい価値のある可能性がつぶれた”と認識することになる。そして部下にしてみれば件の上司は「頼りにならない上司」に映るのは必定である。
「頼りにならない上司」の最たるものが、上通性のない上司である。上通性とは自分よりも上に対して、きちんと意見を言い、獲得すべきものをしっかりと獲得してくることができることである。たとえば、目標達成のための必要な予算を獲得すること、仕事をしていくうえで絶対に必要なルールを作ること、こうしたことを実現するためには、上層部にかけあって認めさせなくてはならない。
当然、上層部には自部署以外の多くの部署からも次々と提案や要望が上がってきている。このため優先順位の下で判断が下される。上層部を動かすためには、常に全体最適の立場から他の部署の責任者をも説得しつつ、自部署の方針を貫徹させることができる上司でなければ、部下にとっては「頼りにならない上司」と映る。反対に自部署の提案がいかに重要かつ必要性について、説得力のあるプレゼンテーションを展開できる上司が「頼りになる上司」に映る。
上層部を動かすことができない上司は、言葉を変えるならば上層部から相手にされていない上司でもある。この種の上司は部下からすぐに見抜かれてしまうものだ。こうした上司の下では、没主体的な部下の中に無為な転職という選択をする者もあらわれる。しかし、上司の力量を見抜いた部下の中で主体的に仕事に向き合う者は、「上司よりも自分がプレゼンしたほうが、提案が通る可能性が高いのではないか」と思考するようになる。
多くの企業では一定の職位層でなければ、意思決定の会議体への出席権限が与えられていない。しかし、たまたま部下の同席が認められた会議体で、上司の説得力のないプレゼンテーションより、出席者全員から無視され提出した提案の可否がなされず放置される光景を目撃するなどした部下は「この上司は本当に使えない」と嘆くことになる。そして、上司としてのガバナンスが効かなくなり、結果として職場崩壊が始まる。
上司のガバナンスが効かなくなる原因は他にもある。それは部下に対する評価や仕事への上司からのフィードバックである。部下の日々の仕事の何を評価して何を評価しないか。これを見れば、上司が仕事の何を見ているかが明らかになる。もちろん不満の出ない評価というものはない。しかし、そもそも評価していることがピント外れであったり、評価の中身が筋違いや事実誤認であったりすると、「この人、何もわかっていない」と部下から見切られることになる。
評価視点のピントが外れている上司は、多くの場合ほぼすべての部下に対してピント外れの評価をするため部下からの信頼を失うことになる。マネジメントでは仕事のアウトプットを評価する能力が必要となる。中身のない見栄えだけよいリポートを激賞したり、時代遅れのコンセプトを「面白い」と持ち上げたり、仕事の本質と関係ないどうでもよい細部やゴシップ的社内風評に左右される評価を行う上司は、「頼りにならない上司」として部下から相手にされなくなる。
| 一覧へ |
![]()