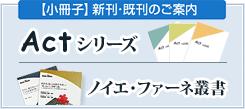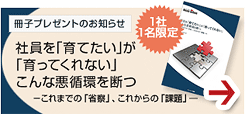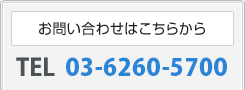人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年01月27日号
OJTによる育成手法の再考-5-権威勾配を踏まえた上手な権限移譲
OJT担当者が有していない知識や能力をOJT対象者(部下)に対して決して伝えることはできない。OJTで相続される内容は、基本的には前の世代が所持しているスキルや知識であり、前の世代が有しているものを伝達することで、業務が達成できることが前提となる。
前の世代は所持していないが今の世代にとって必要な知識やスキルは、OJTでは伝達することはできない。従って、OJT担当者が不勉強(学ばない)であるならば、決して次の世代を育てることなどできない。この点に自覚がなく単なる素朴な経験主義でOJT対象者と接しているなることが、陰に陽にハラスメントの温床となる危険性もある。
組織において上司が部下との関係性を構築するための起点となるは、あくまでも「相手に関心を持つこと」である。上司が部下に関心を持ち、部下の行動特性に合わせた対応を示すことで部下の行動変容が促進される。部下への興味関心から、褒める/叱るという行為が発生するのである。部下の取る行動や言動に対して関心や興味を抱かない上司は、部下を褒める/叱るという感情さえ湧かないはずである。この意味で敢えて批判を恐れずにいうならば、部下に対して「ああでもない、こうでもない」と口を出す上司は、部下への「成長への期待」を下手くそに表現しているようなものである。
同時に上司と部下の関係では“権威勾配”の存在を意識しておかなければならない。組織は上から指示が流れる。従って、階層構造は下(現場)からの意見や情報があがりにくくなる傾向に陥る弊害がある。この結果として、現場が抱える問題が放置されがちになる。新しく創造的な意見が集まらないなどの状況が生じる危険性もある。時には権威が強い立場の人間が傲慢になり、不正や粉飾などのコンプライアンス問題に発展する場合もある。
適正な“権威勾配”は組織にとって不可欠であるが、極端にきつい(急角度)の“権威勾配”が存在するならば、組織の存続にかかわる重大な事象の見逃しにつながる危険性もある。特に特異なスキル・能力を有する者は、自分が意図しなくても、他のメンバーとの“権威勾配”がきつくなりやすい。上司と部下関係ではましてやとなる。
OJT担当者は自分のポジションや組織への影響力を自覚し、“権威勾配”の調整に自覚的に努める必要がある。逆に“権威勾配”がゆるい(低角度)場合は、往々にして、指揮命令関係が曖昧になりOJTが機能しなくなる危険性もある。この種の状況では部下が上長の指示を無視する傾向、できない理由を並べてサボる傾向が発生し、結果的に組織のガバナンスが崩れることになる。
OJT担当者は部下に対して上手に権限移譲をしなければならない。ただし、権限委譲とは、部下に業務を「丸投げ」ないし「放任」するという意味ではない。権限委譲におけるOJT担当者の役割とは、単にルールを決めて部下に従わせることではなく自分で考えさせることである。自らが意思決定を行えるように助言するのが権限委譲である。つまり部下に責任と権限を与え、主体性と成長を促すプロセスである。しかし、このプロセスで「丸投げ」や「放任」になると、かえって逆効果を生む場合が多く厳に戒めなければならない。
権限を持っている者は往々にしてそれを「手放したくない」という心理が働くものである。この心理はOJT担当者にも働く。これは権限が上司の役割や地位と密接に結びついていることに起因している。得てして上席者は“部下に権限を委ねてしまうことで自分の影響力が弱まる”と思い込む。これは権限と権力が同じであるかのように錯覚してしまうからに他ならない。仮に権限が与えられていてもそれが権力を持つことにはならない。OJTでは担当者がこの点をしっかりと認知していなければならない。
| 一覧へ |
![]()