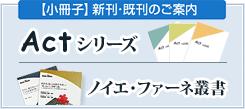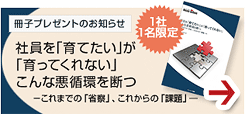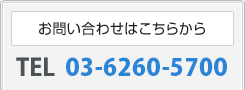人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2024年12月09日号
OJTによる育成手法の再考-2- OJTで教えるべきこと
新人や若手社員に対するOJTでは、「新人がすぐに業績に貢献できるわけではない」ということを前提にしている。もちろん、すべての仕事は業績を上げるために行われているはずである。このためOJTの展開に当たっては、「仕事の基本を徹底させることも業績アップに不可欠なものである」というスタンスで展開されてきた。
OJTは明確で意図的な育成計画の設計がなされていたわけではないが、なぜか上手く機能していたように見えていた。確かに生産現場でのOJTは上手に機能した。この成功経験が生産現場以外にも波及していたったことになる。日本企業のOJTが高度成長期から極めて上手く機能していたように見えたのは、具体的な業務指導とは直接的な関係がないいくつかの条件が重なったからに他ならない。
業務指導とは直接関係がない条件とは、長期間の雇用を可能とした終身雇用と職能制度賃金による年齢上昇に伴う相応の収入増加である。さらにいえば企業組織をあたかも家庭、あるいは“ムラ社会”のように見立てた“従業員は家族と同様だ”ないし“同じ釜の飯を食う仲間”的なメンタリティーが、OJTを機能させる補完物になっていた。そもそもOJTによって継承すべき業務スキルや職務内容が明確に規定されている訳ではなかった。
つまり、OJTによる育成概念が不明確であったということだ。このため、OJT指導が個別の先輩社員による後輩社員への“経験値の刷り込み”と“業務指導”との間の区別が曖昧になっていた。“従業員は家族と同様だ”などと位置づけてしまうならば、OJTと社員への生活指導を混同してしまう傾向さえ生むことになる。しかも、戦後の日本にOJTが定着し始めた時代は、企業を巡る経営環境の変化が比較的緩やかで、先輩社員の経験値の鮮度が劣化する時間も今よりもずっと遅く、誤解を恐れずにいえば牧歌的時代であった。
OJTという指導概念の曖昧化は、往々にして職場で行われる先輩社員や上席者からの諸行為に対しても、OJTというネーミングを貼りつけてしまうご都合主義を発生させることになった。何よりもOJTという指導概念が曖昧で、伝えるべき業務スキルの基準や内容が不明瞭であるならば、OJT担当者の力量が問われることになる。OJT担当者のレベルが不均等であるならば、OJT対象者の成長にバラツキが生じるのは当然である。一昔前までは真顔で後輩社員に対して「酒の飲み方や遊び方を教えるのもOJTの一環だ」などと言いだすOJT担当者も存在していた。今日では論外の極みである。
そもそも上の世代が有していない知識や能力は、OJT指導で決して次の世代に伝えることなどできない。OJTで若手・後輩に相続される内容は、基本的には前の世代が所持しているスキルや知識であり、前の世代が有しているものを伝達することで、業務が達成できることが前提となる。従って、前の世代(OJT担当者)が不勉強(学ばない)であるならば、決して次の世代を育てることなどできない。企業の育成手法としてOJTを機能させていくためには、個別企業において人材育成の概念を明確に規定したうえで、習得すべき業務スキルや職務内容を具体的に提示していく必要がある。
OJTはあくまでも新入社員をはじめとする企業内教育の一環である。従って、OJTの広義の目的は、自分で考えて行動することができる“自立した人材”を育成し、自己管理能力を習得させ自立・自律した働き方ができるようにすることである。
OJTは、「部下・後輩の能力向上とレベルアップを通して組織としての成果を上げる」ために企業が行う基本的な社員教育手法である。従って、OJTは単に「やり方」を教えるのではなく、「やらなければならないこと」「やってはならないこと」を教えることでもある。
| 一覧へ |
![]()