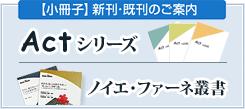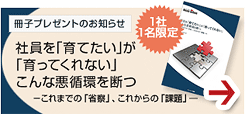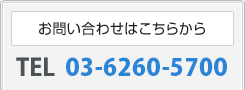人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2024年11月25日号
OJTによる育成手法の再考-1- OJTが上手に機能した理由
OJTは、第二次世界大戦中にアメリカの造船所が大量の人材をいち早く教育する方法として、「やってみせる(Show)」「説明する(Tell)」「やらせてみる(Do)」「確認、追加指導(Check)」という「4段階職業指導法」が原型とされている。第二次大戦後にこの方法が日本に輸入され、何時しか若手や新入社員を対象とした企業内育成の手法の一つとして機能し定着し、今日まで多くの企業で用いられている。日本のOJTは生産現場での職業指導としての側面から生産現場に止まらずほぼすべての職種において用いられるようになった。
一般的に日本のOJTは1人の新入社員に1人の先輩社員がついて業務の報告や指示役を担う形で展開される。企業よっては直接のOJT担当者だけではなく、直属の先輩ではない別の部署の先輩社員が新人にアドバイス的な支援を行うメンター制度を併用している。OJTは基本的に経験を通じて学ぶため、より実践的なノウハウや知識を身につけることができる点が特長とされる。しかし、先輩社員に指導力が伴わない場合、思うような効果が得られない。
日本企業でOJTが高度成長期から極めて上手く機能していたように見えたのは、具体的な業務指導とは直接関係がない要素が重なったからに他ならない。高度経済成長に向かう過程で当時、地方に進出した工場(特に大手メーカーの地方工場)の構成員になった現地の従業員は、基本的に近隣の村落共同体の構成員でもあった。つまり、上司が“村”の構成員で部下も“村”の若者という構成で職場が形成された。職場がそのまま村落共同体の延長線上に存在し、“村”の共同体の構成原理が職場にそのまま引き継がれ持ち込まれていたことになる。
“村”の共同体の構成原理とは単純にいえば「年長者が若手の面倒を見る」というものであり、結果として企業が、「OJTを設計する明確な意図」がもたなくても、その共同体の仕組みや原理を職場に引き継ぐことができたわけである。同時に共同体内に存在していたさまざまな「因習的弊害」も職場に持ち込まれることになった。例えば、古参者の下に中堅や新参者が紐づく上下関係や性別による役割分担などである。これは今もって日本の地方の生産現場で続いている。
“村”の共同体社会において新参者(新たな成人)が共同体(大人社会)に参入する段階で、彼がいつの日か共同体の中心的メンバーになりうるように、適切な仕事が配分され適切な支援・援助が実行されていた。つまり、既に機能している“村”の共同体社会には、新人を育成する機能が暗黙知として仕組みがされていた。この仕組みは未熟な新人を周囲の大人達がフォローし、諸々の経験を積んで徐々に“村”の共同体社会の維持を担う一人前の大人にしていくといういわば「サポート体制」である。
新たに“村”の共同体にデビューした新参者(新たな成人)は、共同体が連綿として続いてきた「村を支える大人」になるための道筋を、当たり前のようにたどることで一人前の大人としての立ち振る舞いを身に着けてきた。ただし、これはあくまでもその共同体で通用する立ち振る舞いであり、ある意味で閉鎖的でもあった。
地方に進出した企業の生産現場では、立地したそれぞれの「共同体の原理」を、そのまま「導入」して活用することができた。このため企業は極端にいえば特段の人材育成投資をしなくともよかった。しかし、当然のことながら機能体としての企業組織と「村の共同体」は基本的に異なる。その最大の違いは「村の共同体」の構成員にはある種の終わりがなく、連綿と続くということである。また、「村の共同体」の構成員は年齢が上がるに伴い役割や発言権(権限)も増してくる。
一方の企業組織の構成員には一定の年齢制限(定年)が存在する。同時に企業組織には明確な役割区分も存在する。このため「村の共同体」の原理を企業組織に導入して新参者を一人前の大人=熟練者にしていくため、“定年までの間は面倒を見る”という終身雇用と、一定の年齢に沿って“相応に自らの存在感を実感することができる”という年功序列という条件と結びつくことが必要であった。(つづく)
| 一覧へ |
![]()