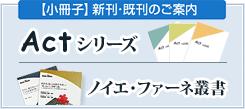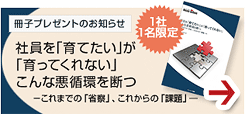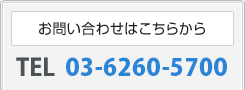人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2024年12月16日号
OJTによる育成手法の再考-3- 部下の“成長の芽”を摘んではならない
日本の企業組織はこれまで基本的に「ハイコンテクスト」で通用してきた。ハイコンテクストとは同じ文化的背景、知識、カルチャーを前提として会話が進むため、言葉の意味をはっきりと明示せず、暗黙の了解や忖度、阿吽の呼吸、以心伝心などで“説明なしでも察し合うことができる”という意味だ。同質性が求められてきた日本の企業組織では、こうした行為ができることで対人関係能力を評価してきた。ほんの少し前まで、多くの企業には「同じ釜の飯を食う」という類のメンタリティーが通用していた。
こうした組織では逆にいえばコミュニケーションを通した「合意形成」が不得手であるということでもある。このため、組織内に円滑なコミュニケーションをとる伝統が形成されず、「みなまで言わなくてもわかるであろう…」という意識が多くの企業に通用してきた。このため組織方針が明確に言葉や文章で周知されず、まして上司からの指示も明確に言語化されて伝わることない。このため、言語化されない不明瞭な指示は、途中で不明確でかつ恣意的な解釈がなされ、結果に対しても曖昧になる弊害の温床になってきた。
明確な言葉や文章による指示がなくとも「場の空気を察すること」が求められた時代の指導で育ってきた世代の管理職にとって、このメンタリティーが全くと言ってようほど通用しない若手・新人に対峙した時に戸惑うのは当然である。この戸惑いを解消する一つの手段として、部下の育成において一時期「褒めて伸ばす」式の手法が喧伝された。これはハラスメント問題もあり、部下指導における一つの手段でもある「叱る」という行為を封じられたハイコンテクストな組織文化で育ってきた管理職にとって渡りに船でもあった。
しかし、実のところ「褒めることによる効果はあまり大きいわけではない」という研究もある。まして自らの曖昧な指示の出し方を内省することなく、単に部下を褒めても何の役にも立たない。無媒介に部下を褒めたところで、賢い部下には体よくあしらわれるだけである。そもそも部下は、嫌いな上司や自分が評価していない上司から褒められたとしても嬉しいと思わない。さらに上司と部下の“日常の関係性”が悪ければ、上司の褒め言葉さえ上滑りするものだ。
上司が部下を褒める目的は、あくまでも部下に期待する“行動”を繰り返してもらうためであり、組織にとって好ましい行動を増やすためである。その前提となるのは上司の側が部下に対し、自らが期待する“行動”の内容を明確に言語化された表現で伝えていなければならない。部下は上司からの明確な指示の下で自らが取った行動に対して、上司から褒めてもらって「嬉しい」と感じたならば、同じような行動を継続的に繰り返してくれる。
上司が部下を褒める基準はあくまでも自らの明確に言語化された指示に対し、部下が行った行動の是非である。もちろん、職場での何気ない対話や雑談を含めた、上司と部下の間で“良好な関係性”が形成されていなければ、いくら上司が部下を褒めたところで部下から“何か裏があるのではないか”と勘ぐられて警戒されるのが関の山である。
上司が部下育成の起点としなければならないのは、部下の行動に関心を持つということである。上司が部下に関心を持ち、部下の特性に合わせた対応を示すことで部下の行動変容が促進される。そもそも部下の行動への興味関心があるからこそ、行動の結果に対して褒める/叱るという行為が発生するのである。重要なことは上司が部下一人ひとりの行動を見守り、ポジティブ、ネガティブの両面から適時・適切なフィードバックを与えることである。
同時に部下一人ひとりが何に対して喜びを見出すのか、何を望んでいるのかについて把握することを厭うことがあってはならない。敷衍するならば相手=他者の行為・行動に対して興味や関心を持つことができない上司は、そもそも良質な“他者との関係性”を構築することができない。結果的にその上司にとってマネジメント業務が負担になり、部下にとっては成長の芽が摘まれてしまうことになる。
| 一覧へ |
![]()