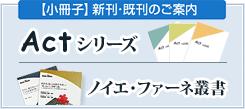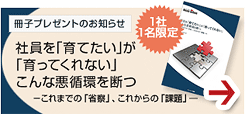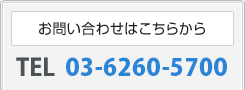人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2022年04月25日号
時代認識と自己マネジメント-2- 時間労働に規定された報酬概念の払拭
人事マネジメントにおいて「働き方改革」がさまざまに語られてきた。とりわけ、長時間労働や残業時間削減の流れと相まって、日本の労働生産性の低さも話題になってきた。一方、日本の労働基準法は労働時間に基づき報酬が支払われることを建前としている。確かに生産量が製造ラインの稼働時間とリンクしている製造業などの業種では、労働の成果を労働時間で測ることが適しているかもしれない。
戦前の工場法を原型とする労働基準法は、敗戦直後の政治状況や日本の産業構造に規定されている。製造業の復活が希求されていた時代には、製造現場の労働時間に基づく報酬の計算にもそれなりの合理性があったかもしれない。しかし、非製造業では労働による成果と労働時間は非対称である。サービス業の分野では長時間サービスを提供し続けたとしても、その成果が必ずしも大きくなるとは限らない。まして、知識労働においては労働時間が成果と結びつくわけではない。
製造業のシェアが高かった時代には、労働時間に基づく賃金決定が社会通念化していたかもしれない。しかし、非製造業のシェアが約8割を占める現在では、時間労働による賃金がむしろ漫然とした働き方の温床となり始めている可能性さえある。乱暴な表現だが残業労働時間の削減を提唱しても、時間労働を前提とした労働法制の下では従業員の意識はなかなか変わらない。これは「メンバーシップ型雇用」から「ジョブ型雇用」への転換論議においても同様である。
盛んに話題にされている「ジョブ型雇用」の内容が、果たして本来的な意味での「ジョブ型」なのか否かも不明瞭である。この不明瞭な点を逆手にとって、臆面もなく「日本的ジョブ型雇用」などという表現を用いる笑止も目につき始めている。決して作為的ではないのであろうが、何かにつけて「日本的」ないし「日本型」などと形容詞をつけたがるメンタリティは、旧態依然とした意識でもある。
好意的に解釈するならば、このように形容しなければ労働時間に基づく賃金決定に慣れ親しんでいる従業員への納得性が担保できないとの思いも見え隠れする。大手企業を中心にした「ジョブ型雇用」への移行が進み始めていると喧伝されているが、一般の従業員にしてみれば一時期の「成果主義」導入と同様に一過性の流行と捉える傾向がある。それは、いくら「ジョブ型雇用」を提唱しようとも「時間労働」という意識が払拭されない限り、従業員一般に腹落ち(ピンとこない)することはないからに他ならない。
ある一定の世代に属する従業員にしてみれば、「ジョブ型雇用」論議がいわゆる「働き方改革」がもたらす当然の帰結であるということにも理解が及ばないはずである。この世代は、1960年代〜1980年代に労働力の中心であった「団塊の世代」によって指導・育成され、そろそろ定年や役職定年を迎え始めようとする世代という意味である。この世代には“自分たちが頑張って働いたから「経済成長」につながった”という「団塊の世代」のメンタリティが何がしかの形で色濃く受け継がれている。
残念ながらこの世代の多くは、「時間労働」と「労働による成果」に必ずしも対称性があるわけではないという認識に至っていない。今日の第4次産業革命と総称される時代では、今までは大量生産かつ画一的に提供されてきたサービスが個々にカスタマイズされる。そして、これまで人間が担ってきた労働の一部がさらに自動化され、労働コストが大幅に削減される。これまで知識労働といわれていた分野においても自動化による労働コストカットの流れが加速度的に進むことは必定だ。
そして「ジョブ型雇用」の展開は、職場に明確な階層化をもたらすことになる。単純化すれば定型業務と非定型業務との区分が明確になるということだ。定型業務であれば時間労働による成果を前提とした発想は通用する。しかし、この種の業務は企業組織において低層に位置づけられる。少なくとも自らが非定型業務に従事していると考えている者にとっては、自らの時間労働の掛け算が成果であると捉える発想を払拭しなければならない。
| 一覧へ |
![]()