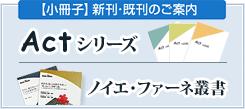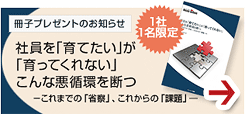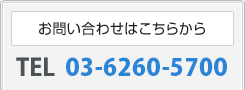人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2019年10月21日号
組織の帰趨を担う覚悟で部下育成にあたる
上司は部下を評価するにあたり明確な判断軸を持っている必要がある。何故なら部下にとって評価されることは、自らの成長意欲を大きく左右するからである。このため上司として部下を評価する基軸を明確にしなければならない。情意が先行するならば結果的に公正性を欠いた評価になってしまう。
評価基軸の一つは、「部下同士を比較して評価しない」ということだ。部下同士を比較して、どちらかに軍配を上げるようなことをしては、低く評価された部下は意欲をなくすのは必定だ。評価にあたっては一人ひとりの強化する時間軸を決め、一定期間内での成長度合いを見て判断しなければならない。
一定の期間に個々の部下に課した課題に対して、部下がどのように取り組み、課題をどの程度達成されたのか。また、前期と比較して課題達成に向けてどのような進捗面での成長があったのか。これらを具体的な数値に基づいた指標に沿って評価しなければならない。数値基準と同様に仕事の質に対する認識の度合いも評価軸とする必要もある。
ビジネス上の成長とは、作業と仕事の割合の変化でとらえることもできる。仕事とは「付加価値を生むこと」である。一方で作業とは付加価値を生むための手段にすぎない。ところが、部下に限らず価値を生む手段である作業を「自分の仕事である」と理解している者が多い。こうした理解は仕事を「与えられたものをこなす」という意識にとどまっている証左でもある。
部下の育成とは、一面では作業から仕事へと、部下の行う業務の質を高めていくことである。部下を仕事意識に目覚めさせ、付加価値を追求するように仕向けていくことが、管理職の重要な役割であり責任でもある。部下の未熟さを嘆く前に管理職は、如何にして部下の成長意欲を高めていくのかに注力しなければならない。管理職が部下を放置したままで個々の部下に対して「できる」「できない」を評価するのは、指導を放棄した本末転倒の評価姿勢である。
管理職にとって部下の育成は忍耐をともなうものであると覚悟する必要もある。部下の育成を放棄して「使える部下」「使えない部下」に分けて、使えない部下を排除している限り、組織をあずかるものとしての管理職自身の成長はない。この意味で管理職にとって部下の成長と評価実践は、まさしく「自分事」である。
部下を「使える」「使えない」に分けて、使える部下だけを重宝することは、誰にでもできる。また、単純な「使える」「使えない」という発想では、現状に合致していたとしても企業組織の将来性を見越していないことになる。確かに単純な「作業」を行うのであれば、この基準も通用する。しかし、この種の手法の繰り返しでは企業組織を担う基幹人材が形成されず、組織力が高まらない。
現状の雇用制度の転換期において、企業にとってその時々の状況に合わせて、いつでも不断に使える人材が外部から調達できる状況とは限らない。従って部下を最大限成長させて、組織力を高め、基幹となる人材を育成することが企業にとって必要となる。管理職は部下の育成にあたり、組織の帰趨を担う誇りを持って臨んでいく覚悟を持たなければならない。
| 一覧へ |
![]()