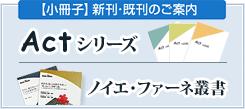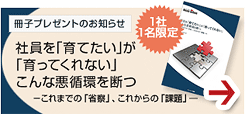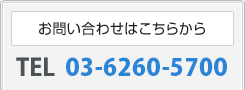人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2018年05月07日号
管理職にとって“意見する部下”は心強い存在
部下が上司の顔色をうかがうのは至極当然のことである。これは一般社員に限ったことではない。課長は部長の顔色をうかがい、部長も経営陣の顔色をうかがう。そして経営陣はトップの顔色をうかがう。それぞれの段階で悪しき忖度が始まり、無意識のうちに組織の上層は階層が上位であればあるほど現場から乖離し始める。
一方で中小企業などではトップと一般社員の距離が短いため、一般社員が中間に位置する管理職を飛び越えてトップの意向を忖度する傾向が強くなる。このため、何時しか中間層のガバナンスが機能しなくなる。一昔前であれば、忖度も“察する”という意味で用いられてきた。しかし、顔色をうかがうという忖度は、機能不全の温床にもなるから危険である。
もちろん、忖度も“周囲を慮る”あるいは“察する”という意味であれば、組織が円滑に機能する上で重要にことである。昔流にいうならば“一を聞いて十を知る”という部下の存在は、上司にとってありがたいことでもある。しかし、企業組織でマネジメントを司る管理職層が、部下にことさら“一を聞いて十を知る”を期待することは過剰な要求でもある。
とりわけ、こうした行動がとれない新入社員に向かって、“能力が欠如している”と捉えることは誤りである。今日では“一を聞いて十を知ることは能力と別次元である”との割り切りが必要だ。そもそも若手社員に備わっていない能力を期待する管理職層は、時代変化に背を向け自らの経験を単純に懐古し、比較優位性を保持しようとする行為に等しいといわなければならない。
残念なことだが今日の若手社員は“周囲を慮る”あるいは“察する”行為が持っている優位性を理解できていない。また、このような行動をとる必要性もなく育ってきている。しかし、“上司のいうことは聞かなければならない”という規範意識が欠如している訳ではない。むしろ上司の指示を無批判に聞き入れてしまう傾向さえある。
問題はこうした部下の存在に対して上司の側が満足してしまうことだ。上司にとって「いうことを聞かない部下」よりも「いうことを聞く部下」の方が使い勝手が良いと思いたちだ。ここに大きなマネジメントの落とし穴がある。つまり、“上司の行動や考えを慮った行動”をとるのではなく、“上司のいったこと、いわれたこと”をそのまま行うということだ。
これは“上司の顔色をうかがいながら”自らの行動を選択するのではなく、上司が誤れば皆が誤ることに繋がる。組織活動において上司の判断に対して自らの判断や考えを加味することなく無批判に従う行為は、非常に危険なことである。何故なら組織の発展や自らの成長に対する無責任になるからだ。結果的にこの行為は上司が時として組織のルールや規範さえ逸脱させてしまう危険性もある。さらに組織の一員としての居心地の良さを重視することになり、個々の成長意欲を萎えさせることにもなる。
「上司の指示を批判的に捉える」とは単純な反発ではない。あくまでも自らの属する組織に対する発展に責任をもって参画することと同意語でもある。つまり、批判的な精神を堅持して自らの考えを表明することは、組織に対して貢献意欲を堅持するということでもある。上司にとって「なんでも上司の指示に従う部下」の存在は、マネジメントの質の向上や組織の組織性を阻害することになる。「上司に意見をする部下」の存在は上司のさまざまな判断に対するリトマス試験紙でもある。
| 一覧へ |
![]()