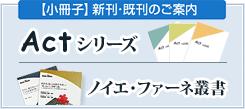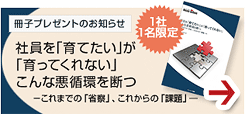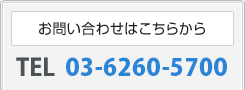人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2015年10月05日号
管理職の評価実践は部下の育成と同じである
管理職にとって部下の評価は適正でなければならない。これは一人ひとりの成長度合いに見合った評価でなければならないという意味だ。ところが実際にはこの至極当然な事柄が遵守されていない。この理由の多くは管理職自身が明確な評価基軸を持っていないことによる。
自ら明確な判断基軸を持っていないため、評価実践では「可もなく不可もなく」との評価が横行する。特に評価結果を段階で表示するような「評価システム」が確立していればいるほど管理職の評価基軸が明確でなければ、評価が曖昧になる危険性がある。
管理職による部下の評価は、部下自身の成長意欲に直接的に影響するものである。日常的に部下の「できている事」「できていないこと」「今後伸ばしてもらい能力」「改めてほしいと思う職務態度」に対して、適時適切なフィードバックを展開しなければならない。
日常的なフィートバックを怠り年に数度の「評価実践」の場で、誰彼の区別なく一応に「可もなく不可もなく」を繰り返してはならない。また、一律に評価することがあたかも公平であるかの悪しき平等主義に陥ってはならない。“部下に優劣をつけたくはない”という心理は、安定した成長が保障されていた時代の弊害であるともいえる。そもそも他者に対する評価は、評価する側に大きなストレスとなることは確かだ。このため部下の評価にあたって管理職は、部下の顔色を窺うことなく自らのブレのない判断基軸を明確に持つ必要がある。
管理職が部下評価で最も意識しなければならない事柄は、“相対評価をしてはならない”ということだ。相対評価とは、成績順位に対して上位5%の人を「S」(5点)評価とし、順に上位5〜25%の人を「A」(4点)、25〜75%の人を「B」(3点)、75〜95%の人を「C」(2点)、95〜100%の人を「D」(1点)という具合に分布率を設けるということだ。
部下評価に相対評価の意識を持ち込むならば、往々にして中間の分布に評価が集中するものである。この結果、全員の評価がほぼ同じになる傾向がある。しかし、日常的な業務実践の過程で部下の成長には優劣が発生するのは当然の結果である。管理職にはこの優劣をはっきりと部下に自覚させていく必要がある。もちろん、業務上の優劣であり人格上の問題とは全く別物である。このため、評価は「絶対評価」でなければならない。
管理職が部下に対する評価軸で重視しなければならない事柄は、作業と仕事の違いである。一言でいえば、「付加価値を生む仕事」をしているか、「付加価値を生むための手段である作業」に終始しているのかの見極めだ。部下に対しては、常に自分の「仕事と作業の割合」を意識させていかなければならない。たとえ遅くまで残業を繰り返し、本人が「頑張っている」と思ったとしても、それが単なる「作業」に終始しているのであれば意味がない。
管理職の評価軸が明確であれば仮にある期間で低い評価となった部下であっも、改善すべき課題や習得すべき職務能力を自覚することができる。そもそも自らの業務評価に対する自覚がない部下は、“成長意欲が萎えている”という割り切りも必要になる。
管理職の評価実践とは部下への成長すべき課題の指摘であり、部下を仕事意識に目覚めさせ、付加価値を追求するように仕向けていく育成である。
| 一覧へ |
![]()