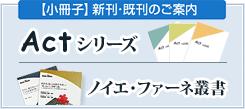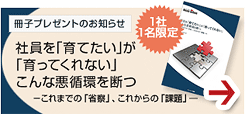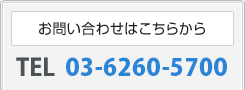人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2011年03月28日号
「これまでと同じ」という発想が会社組織を堕落させる
ひとは自らが育ってきた環境に規定されてしまうものだ。これは単に家庭環境にだけいえることでしない。企業人、組織人は最初に属した組織環境にどうしても影響を受ける。よくひとは「最初の職場での体験が大きく左右する」であるといわれる。
また、「最初に指導された上司の善し悪しで、就労意識や仕事スタイルが決まってしまう」といわれる。要は一旦身に就いてしまった悪い体質やクセを払拭していくのはなかなか難しいということだ。
会社組織も同じことがいえる。組織の草創期は組織全体が色々な思考錯誤を繰り返していくため、自分の行う業務範囲の変化や新しい仕事内容が増えることそれ自体が日常と受け止められる。そして、時を経るにしたがって、組織人員も増加し業務部門も細分化され始める。一人ひとりの社員が担当する業務内容も固定化しはじめる。
こうした経緯は正に会社組織の発展として受け止められる。なぜなら部門の確立や一人ひとりの担当部署の明確化は、組織体として効率化されてきたと受け止めるからだ。
しかし、ここに落とし穴もある。組織体として個々の部門や担当部署の業務領域を明確して、効率化(分業化)していくことは、それぞれの領域を守るという意識が芽生えてくるからだ。つまり、与えられた自部門や部署に長く従事すればするほど、愛着と同時にそれぞれの構成員の中に「既得権意識」が生まれてくるからだ。
会社組織内の「既得権意識」とは当該部門にとっての「合理的」判断の帰結でもあり、長い社歴の中で部門・部署、あるいは個人に蓄積されてしまうものだ。たとえば、会社組織には往々にして、どう考えても非効率な作業や誰が始めたのかは全く不明だが、なぜか誰もが踏襲している行事などかある。
こうしたことを改めようとすると、なぜか何処からともなく圧力がかかり、改革の動きが潰されてしまことが起こる。こうした現象は各部門での「合理的」と思って行う行為が、全体として「不合理」を生みだし、組織全体を「不条理」な行動に走らせてしまうこともある。
明確な反対が表明され公然とした議論が沸き起こるのであれば、組織体としては活性化しているので問題はない。しかし、どこで、誰が決めたのかも不明なことが、暗黙の了解として「噂話」のように広がりはじめ、外部から見て「不条理」と思えるこうした段階に至ると、組織体は死に体と化していくものだ。
会社組織が死に体に陥っていくのは、組織を構成する一人ひとりの「これまでと同じ」であることに安住してしまう意識だ。仕事上で「これまでと同じ」ことを繰り返すことは、非常に楽なことでもある。そして、自らの「既得権」を守ることでもある。しかし、こうした意識は劇的な環境変化に対応できなく絶滅した恐竜と同じ道が待っている。
| 一覧へ |
![]()