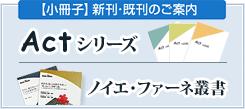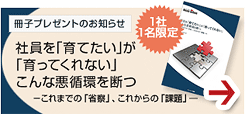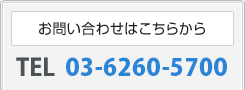人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2013年02月18日号
自ら『習い性と成る』に陥ってはならない
「習い性(ならいせい)と成る」いう諺がある。語源は『書経』により、家臣が君主(王)に忠告としていった言葉であるとされている。意味は、毎日、続けている習慣は、やがては、あたかもその人の生まれつきの性質のようになってしまうというものだ。
良い習慣も悪い習慣も同様だ。悪い習慣が身につけば、それが、その人の性質になり、良い習慣を身につければ、それもその人の性質になってしまう。修身ではないが、良い癖をつけるか、悪い癖をつけるかは、その人の心がけしだいで、変わるということだろう。
ところが、この「心がけ」というものが実に厄介な代物だ。得てして悪い習慣が表面化して自らの行動にあらわれてしまうものだ。
上から与えられた仕事を単にこなすことに終始し、自分では責任をとらないという姿勢をとる者を「サラリーマン根性」に毒されていると表現することがある。しかし、「サラリーマン根性」は、悪意を持って意識的に形成されるものではない。長い期間にわたり「会社の方針や方向性は会社(経営陣)がすべて決定するもの…」「個々の社員は会社(経営陣)からの指示を効率よく実践することが自分の職責を果たすこと…」などという意識がいつしか無意識化して“習い性”と成った結果だ。
この“習い性”は、一人ひとりの「役割遂行」が、組織で働く個々人に課せられた個としての問題でもあるという意識を形成させることなく、自らの役割意識を組織に従属させることが「組織人の働き方」であるかのような錯覚を植え付けてきた企業側の育成結果でもある。
もちろん、この育成結果のすべてが個別企業に責任に帰する訳ではない。むしろ十分に機能した時代もあったし、時代背景のなせる業でもあったことだけは確かだ。しかし、この“習い性”はいつしか、企業組織で働く者の中に「依頼心」を助長させ、自分の頭で物事を考えることなく、常に組織の一員であることへの安住として、受け身の「行動」でよしとする風潮を生んできた。
時代背景で形成されたといっても実は1955年以降の高度成長を経て1980年代まで続いた僅かな期間の日本経済の「成功の軌跡」によってもたらされたものに過ぎない。この期に形成された受け身の行動規範が“習い性”として、多くの企業で働く者の意識を規定してしまった。
この行動規範を払拭していくためには、まず会社組織や仕事上で発生していることに対して、その現象や実態を徹底的に自分の頭で考える癖をつけることだ。
考えるとは、夢想することではない。「与えられた条件の中で最善となるべき判断」を行うためには何が必要かという思考するということだ。同時にそのためには判断する(考える)材料=情報を集めて分析を行うことだ。そしてその判断材料に基づいて推論を立てて検討し、集約して結論を出すことだ。
こうした行為の繰り返しからおのずと、今現在の自らの仕事に対する姿勢の反芻が生まれてくる。同時に自分の仕事に対する「意味つげ」も生まれてくる。自分で「自分の仕事に対する意味づけ」を行うことで、他者との議論も生まれてくる。当然、議論の過程で他者との間で意見の相違も発生するかもしれない。他者とは同期同僚に限ったことではない、広くいえば会社組織全体という意味でもある。
「自分の頭で考える」ということが、「事なかれ主義」での仕事スタイルを払拭する近道だ。
| 一覧へ |
![]()