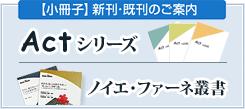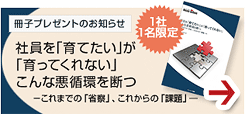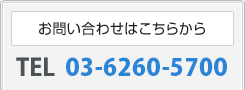人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2023年09月25日号
マネジメント行動の再検証-15-若手は「組織内のお荷物」をロールモデルにしない
日本の高度成長期はとっくの昔に過去のものとなっている。しかし、その幻影は企業組織に未だに蔓延っている。高度成長期は社会全体の成長に規定され国内消費が拡大していたため、乱暴にいえば精緻な経営戦略やビジネスモデルなどがなくとも“作れば売れる”という特異な時代でもあった。このため、企業の人事マネジメントなども極端にいえば不要であり、単純な労務管理や正社員クラブ化した労働組合対策に終始することで済まされてきた。
この時代を経験した世代は部下指導においても精々のところ「今日もみんなでガンバロー!」と鼓舞してさえいればよかった。そして部下もこうした指導・育成概念に乏しい上司・先輩の背中を見て真似ることで済ますことができた。こうしたスタイルは次の世代にも受け継がれてきた。そして、この意識から抜けられない世代が、今日のZ世代と称される若手社員を前にして立ち竦んでいる。
日本企業は高度成長期において若手をはじめ、従業員への育成負担も知れたものであった。そもそも育成を投資などと位置づけず単なるコストであった。何故ならば毎年入社してくる新入社員に対し、数年次上の先輩や末端の役職者をOJT担当者に据えて、その者たちのやり方を真似させるだけで良かったからである。新入社員もまた、先輩やOJT担当者からの時に理不尽で非合理的と思われるやり方に、内心では不満を持ちつつも真似ることに勤しんできた。
その理由は簡単である。自分も先輩や上司達の年代に達したならば、同じような処遇が保障されると信じていたからである。こうした意識が日本企業に根付いた年功序列や終身雇用の底流である、といってもあながち外れてはいない。同時にバブル頃までに存在していた“企業は従業員の共同体だ”“企業は家族”という意識と結びつき、従業員の就労意識を規定するものとなった。しかも厳しく制限された日本の「解雇制度」がこの意識に拍車をかけてきた。
企業にとって年功序列は従業員を処遇や賃金面から定着させるうえで、非常に便利な制度として機能してきた。年功序列は端的にいえば、若手には貢献度にかかわりなく安い賃金で働いてもらい、年長になればこれまた貢献度にかかわりなく若手よりも高い賃金を支払う仕組みである。若手にとっては自分が若い間に作った企業への「貸し」を年長になってから返してもらう制度である。従って、若手にとっては途中で退職したならば、それまでの企業への「貸し」が回収できなくなってしまう。この意味で企業と従業員の瞞着的な関係でもあった。
今日、グローバル化と称される「競争原理の変化」は、企業経営においてこうした牧歌的な意識を一蹴することなった。例えば「定年後再雇用」制度によって一見すると高齢人材の雇用確保が進んでいるが、逆に企業内では「役職定年」の時期が早まり始めている。つまり、定年延長などによりベテラン社員の比率上昇を抑制する手法としての「定年後再雇用」でもある。そして、何よりも「解雇の金銭解決」の制度化も射程に入ってきた。こうした流れに対して高度成長期の残滓がある世代の意識変容は残念ながら極めて鈍い。
残滓とは没主体的にしか企業組織に関わることなく、何とはなしに従っているならば「何とかなるだろう…」という自律した働きに徹することができない意識である。こうした発想では自らの働きに自信を持つことなく、いつまでも「働かされている」という意識に留まっていることになる。こうした意識にとどまっている者に限って、若手社員が発する働きに関する「なぜ、それをやる必要があるのか」「それをやる意味や効用は何か」という類の疑問や質問に対して、主体的な回答に躊躇してしまう。
ビジネスにおいて唯一の正解があるわけでもなし、組織内の人間関係においても同様である。企業組織での働きは、唯我独尊で自分一人が行うものではない。意見の異なる者であったとしても共通の目的に向かって協働して進むものだ。しかし、誤解してはならないのは「協働」するということは、「みんなと一緒」という意味ではない。一人ひとり自律した働きがなければ、決して「協働」にはならない。自らに自律した働きの意識を持たない者は、企業組織にあっては単なる「お荷物」的な存在になるのが必定だ。そして、何よりも今日の若手は「お荷物」的な存在を決して自らのロールモデルなどにはしない。
| 一覧へ |
![]()