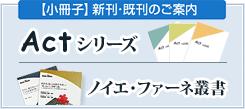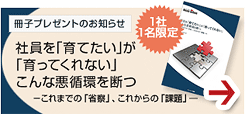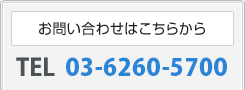人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2023年05月08日号
マネジメント行動の再検証 -1- 部下育成とは自省という負荷
新入社員が職場に配属される時期である。この時期になると相も変わらず新入社員の“トンデモぶり”が面白おかしく語られる。しかし、新入社員からは配属先の上司や管理職の「トンデモぶりにも辟易している」との答えが返ってきそうだ。もっともそのような内容はSNS上では広く出回っているのだろうが…。新入社員にしてみれば自分の上司など選べない。巷間いわれる「配属ガチャ」ではないが、同じ部門であっても直属となる上司や管理職に「当たり、ハズレ」感を抱くのは当然でもある。
これは新入社員にとって極めて不幸なことである。同時に直属となる上司や管理職にとっても不幸なことである。何故ならば上司や管理職は新入社員に対する接し方の訓練を受けていないからである。接し方以前に部下を育成することが自らの役割であるという意識が未形成であるからだ。そもそも育成の意味や位置づけについて明確に認識されているかも疑わしい。このような状況で自らの下に新入社員が配属された上司や管理職は「面倒である」とネガティブな発想に陥るのが必定である。
今も昔も管理職に求められる能力の中で最重要項目は、新人に限らず部下を成長させることに変わりはない。ただし、一昔前であるならば新入社員も含めて企業組織内には、ある種の同質性が保持されていた。このため、管理職にさほどの育成スキルが備わっていなくとも新入社員は、時間経過により相応になんとなく組織の色に染まることが、あたかも仕事が出来るようになったかのように錯覚してきた。要するに「背中を見て育つ」式の牧歌的なスタイルが通用してきた。そしてこの手法の下で「自らが育ってきた」と認知している管理職にしてみれば、残念ながらこの手法しか知らない。
部下に見せなければならないのは「背中」ではなく、具体的に信頼に足りうる存在としての立ち振る舞いと業務行動のロールモデルである。企業組織は自らの存亡をかけて必死に次の一手を指向しなければならない。これは単に経営陣の問題だけではなく、企業組織を構成する一人ひとりに課せられている。何よりも管理職自身が自らのこれまでのものの見方や思考方法、これまでの手法に対しての再考を必死に追求しならなければ、自己の存在価値を示せない。
新入社員も同様である。先ずは入社した企業で必死にキャリア形成をしなければ、自らの将来を切り拓いていくことはできない。今日の新入社員は「いわれた事柄」を単純に繰り返していく仕事ぶりが評価されないことを承知している。このような働き方では自らの成長につながらないことも認識している。恐らく、新入社員の認識は企業内で安穏としている層の認識をはるかに凌駕している。この認識は新入社員が健全に抱く危機感でもあるからだ。
企業組織は新入社員に限らず自ら成長する意欲のある者を評価する。何故なら業務能力と職務意欲が育成されていない集団は、生産性が低いだけではなく俊敏な組織性を発揮できないからだ。管理職には部下を育成することが求められているが、自らがその任に適しているか否かを問い直すことも重要となる。また、育成とは部下を成長させるだけではなく、自らが成長する厳しいプロセスであると受け止める必要がある。
最近では部下育成において「鍛える」という言葉が「死語」と化してきた。しかし、鍛えるとは育てることと同義語であり、管理職が部下の能力を高めるために多少の無理を課すことも必要となる。さらに管理職が部下育成を担うためには自らの自省が根底になければならない。部下育成とは理念や目標を共有し、仕事の意義や価値を教え、喜びを感じられる職場環境を整備することでもある。
部下の意欲を高め、成長を促すには、これまでのように同質性思考に基づいて求められてきた「会社のために頑張ろう」というフレーズでは通用しない。一人ひとりの仕事の社会的な意義を強調し、仕事の意義を自覚させて企業組織における自分の存在価値を実感できるように促していかなければならない。管理職にとって部下育成とは自らが“部下の成長に責任を担う”と同時に自らが“従来思考を自己変革させる”いう負荷を意識的にかけていくことである。
| 一覧へ |
![]()