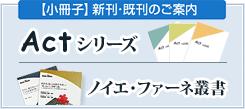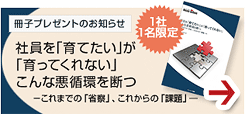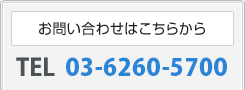人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2021年10月04日号
高齢者雇用と中高年の再就職 −4− 問うべきはパフォーマンスの高低
「国としては70歳まで企業に雇用を義務づける方向でお願いしている」とは、9月9日に行われた経済同友会セミナーにおけるサントリーHD・新浪社長のいわゆる「45歳定年制の提言」に対して加藤官房長官(当時)の記者会見での発言だ。新浪発言が何処まで熟慮したうえでの発言なのか否かはともかくとして、政府の掲げる「70歳までの継続雇用」の義務化と実際の企業経営における肌感覚のズレが明確になったことだけは確かだ。
改めて指摘するまでもなく政府の「70歳までの継続雇用」は、あくまでも「年金受給時期の延長」を主眼にしたものである。しかし、実質的に大企業では「45歳」を分岐点として、その後の処遇が選別的に展開されているのは周知の事実でもある。新浪発言に対して一部には「雇用不安になる」という批判がネットを中心になされていたが、これは今日の大企業における雇用と処遇の関係性を踏まえない単なる感情論である。
是非はともあれ日本の雇用制度が「メンバーシップ型雇用」から「ジョブ型雇用」へとシフトしていく過程にあることは間違いない。そして、これは2018年の「働き方改革関連法」の成立によって明確な流れとなっている。なによりもジョブ型雇用は日本企業の定年制と相性が悪いものである。「仕事に人が紐づくジョブ型雇用」においては、体力的な要素を別にするならば働きが年齢に左右されるものではない。一定の年齢を境に職務能力が極端に減退するわけではない。ある仕事(適所)に対してその仕事に見合った人(適材)を配置すればよいだけのことである。
ただし、これはあくまでも評価の基準が、個々人の生み出すパフォーマンスによって測られることを前提にした場合である。しかし、経年によって「職務遂行能力が蓄積されるはずである」という年功意識に基づいた職能給では、現実の職務能力に裏打ちされたパフォーマンスを適正に評価することができない。極端にいえば企業にとってはパフォーマンスの高い高齢者であるならば、高額の報酬を提供したところで問題にはならない。パフォーマンスの高低に年齢差などない。
企業が報酬の基準をパフォーマンにするならば、パフォーマンスの低い者に対し年齢に関係なく、低い報酬で処遇することは当然のことである。この意味で定年退職後の継続雇用者に対して一律に現役時代よりも低い報酬で処遇するという行為は、ジョブ型雇用における報酬と矛盾する。仕事に対する報酬という視点に立てば年齢差別は不公正となる。このような年齢差別が維持されているのは、日本における「メンバーシップ雇用」が年功賃金により高齢者の雇用がコスト高になっているからに他ならない。
併せて、現状の労働法制において個人の仕事能力の不足による解雇が、裁判では「解雇権の濫用」として厳しく制約されていることも大きな要因である。つまり、仕事の能力が企業の求める基準に達していなくとも「定年まで雇い続けなければならない」という負担の軽減措置としての定年年齢の設定であるとみることもできる。定年制はある意味での「合法的解雇」でもある。
個々の従業員においては、入社してから企業内での訓練を積極的に吸収し、自分のキャリアを主体的に形成することに励んできた者と、単に上司の指示に対して受動的な対応に終始してきた者との差は、年齢が高まるとともに拡大する。このため勤続年数が長くなるほど、同一年齢の高齢者間の仕事能力のばらつきは大きくなることだけは確かである。これは過去の高い経済成長期に形成された長期の雇用保障自体に内在する宿痾である。
定年の年齢を定めることは、従来の日本の雇用慣行である長期雇用保障の見返り措置でもあった。しかもこれは、従業員の「働きの質」に大差がないことが暗黙の前提として成り立ってきた。現実に仕事能力に大きな幅や差のある従業員を画一的に「定年」にして、一律に報酬を下げる手法は、人事上の非効率性と不公平性を欠いている。個々の従業員の「働きの質」、パフォーマンス結果の高低を問うことなく、仮に定年年齢の延長や継続雇用を70歳まで延長したならば、職場にはますます世代間矛盾が蓄積されるだけである。
| 一覧へ |
![]()