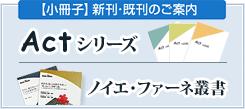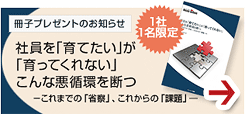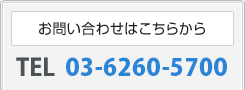人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2021年09月13日号
高齢者雇用と中高年の再就職 −2− 継続雇用者へのマインドセットと組織整備
「就業構造基本調査」(総務省)によると、「働きたいが働いていない高齢者」の割合は、60〜64歳が15%である。これに対し、65〜69歳が22%、70〜74歳が27%と、年齢を経るごとに高くなっていく。この数値から定年後も働く意欲はあるが、現実的に雇用の場が存在していないと解釈できる。もっとも本人が「働きたい」と思いつつ、希望する職種との間に齟齬があると捉えることもできる。
法改正によって「努力義務」とはいえ70歳までの雇用延長(あるいは継続雇用)となった場合、企業が真っ先に考えなければならないことがある。それは、従業員の高年齢化が組織に与える弊害だ。これは単に年齢に伴う肉体的、健康面への配慮という意味だけではない。企業は高齢者雇用の拡大に備えて、目的意識的に人材配置を組み替えていく必要がある。それは人材再配置をしなければ、長期にわたり同じ業務に居座ってしまう者が増え続けることになるからだ。とりわけ、中小企業ではこの弊害が大きくなることが危惧される。
定年後の継続雇用者が同一職場に存在することが、若手社員のモチベーション低下につながるケースが多いためなおさらである。薄れてきたとはいえ日本社会にはまだ、「長幼の序」という発想が存在し、職場にもこの傾向が色濃く残っている。もちろん、一般的に年長者を敬うことは決して否定されるべきではない。
一方で企業は継続雇用者に対して、表現は不適切かもしれないが「老いては子に従え」という精神性を求める必要もある。何故ならば、継続雇用者が今は上司となっている「かつての部下」に対して、指導と非指導の関係に転換したことを踏まえず「上から目線」で接するならば、職場のガバナンスが一気に崩れてしまうことになるからだ。職場ガバナンスの崩れは企業組織にとって致命傷になりかねないため、最も注意する必要がある。
ビジネス現場においては、あくまでも一人ひとりの働きの度合いや貢献度が計られる。この至極当然の論理は、ともすると従来の雇用制度の下では二の次になり、「仲間意識」の醸成と二律背反のように位置づけられてきた。これは1990年代後半に日本の一部企業で中途半端かつ未消化に導入された、いわゆる「成果主義」に起因するところが大きい。しかし、継続雇用者が時代変化を主体的に受け止めることなく、「70歳まで雇用されて当然である」という意識に陥った瞬間に自らを「単に存在しているだけの状態」に落とし込めることになる。
企業にとって継続雇用対象者への意識変容を促す再教育は不可避となってくる。つまり、「第二の新入社員研修」を施す必要があるということだ。これは企業が産業構造の変化や新しい動きに臨機応変に対応していく、人事面におけるリスクマネジメントの一環でもある。何故ならば継続雇用者の存在は、企業全体の適正な人員構成や新規採用の展開と密接に関連してくるからだ。また、継続雇用者と現役世代の賃金を若手に不公平感を抱かせることなく調整する賃金体系等の再設計も重要となる。いうまでもなく継続雇用者であるからといって労働法制の適用範囲が変わるわけではないため、就労意欲の恒常的な把握と健康管理、安全管理には一層の配慮をしなければならない。
企業にとって70歳までの継続雇用は、従来の人事マネジメントの範疇では対処できない多くの問題が発生することを覚悟しなければならない。企業には継続雇用者を抱えながら組織の生産性を向上させる仕組みを整備する課題が重くのしかかってくることだけは確かだ。
この仕組み整備おいては、継続雇用者への意識変容を促すソフトランディングを基本としつつ、単に「存在しているだけ」の不良継続雇用者に対し、ハードランディングで対処することも含まれるということだ。さもなければ70歳までの雇用延長をめぐる混乱があちこちの企業で起こることが予想される。この意味で継続雇用は今後の企業の人事マネジメントの帰趨を左右する問題といっても過言ではない。
| 一覧へ |
![]()