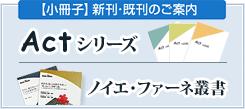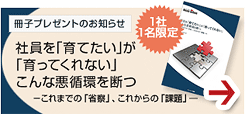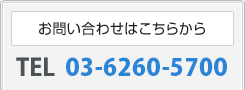人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2020年07月13日号
分岐点に立つ覚悟-7- 働くことへ誇りと信念の堅持
いまでは、企業が「社会への貢献」や「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」を謳うのが一般的になっている。テレビのCMなどでも環境保護活動への貢献、地域社会への貢献をことさらに強調するモノが非常に多くなっている。いや、せざるを得ないという表現が正しいのだろう。
こうした動きを「一過性のものだ」と嗤うのは簡単だ。しかし、こうした「社会への貢献」という意識が、働く現場にも大きな変化を起こし始めている、という点に注目する必要がある。とりわけ新卒採用現場では顕著になってきている。
特にこれから就職を控えている学生や、若手社員に広がりはじめている「就労意識」の変化に見てとることができる。高度経済成長期の残滓ともいえる就労感や意識に慣れ親しんでいた者からすれば、今日の若者たちの「就労意識」を怪訝に思うのは当然だ。
ただ、ここでいう「就労意識」の変化とは、モラトリアムという意味ではない。マスコミでは若年者の就職難という状況から、「就職しない・できない」学生の問題を取り上げがちだ。しかし、「就労意識」の変化とは、実際に就職する段階での企業選択や、就職先での自らの「働き方」について、一つの特長があらわれはじめているということだ。
その特徴とは、「なぜ自分は働くのか」「誰のため、何のために仕事をするのか」ということを真剣に問い始めているということだ。そして「社会の為になる仕事をしたい」ということに結び付ける。実際に求人広告で「実力次第で、○○万円以上の年収も可能」などという宣伝文句には、もはや全く見向きもしなくなっているのは事実だ。
これに対して昭和的な価値観で「ハングリー精神が欠如している」と嘆いてもまったく意味がない。今日の若者が求めるのは、仕事から得られる達成感や仕事を通した自分自身の成長、新たな人との出会い、他者との関わりでの自分の果たしている役割を重視している、といっても過言ではない。こうした意識に対して、現場で日々の仕事に汲々としている側からするならば、「何を青臭いことを今さら…」という批判の声が聞こえてくる。
彼ら(彼女ら)にとっては、いたって真摯な課題であるということを理解する必要がある。これはかつて日本の職場で当然に語られてきた「働きがい」の重視や「働く喜び」の体感という意識の再来とも捉える事ができる。誰しもが「仕事」は、単に「お金の為だけ」とは思っていない。お金は生活の糧ではあるが、それ以上に「仕事の喜び、楽しさ」を求め、自らの働きが他者から評価・認められたいと思うものだ。
働くということは、自らの誇りと信念をよりどころにしなければ、単なる苦役に終わってしまうものだ。若手社員の就労観の変化に対して、既存の従業員が自らの働きに誇りと信念が問われることになる。そして、既存従業員が自らの働きに対する誇りと信念を表出できない職場であるならば、若者に去られても当然という時代でもある。
| 一覧へ |
![]()