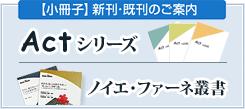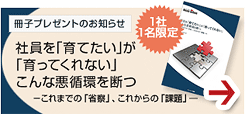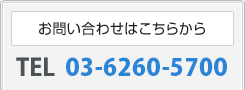人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2016年03月14日号
管理職の言質・行動は新人・若手から監視されている
管理職は新人・若手に対して先ず“「働き方」について自分自身と会社組織の関係”を明確にするように教えなければならない。その際に会社とは、“社会と人間にかかわる組織体である”ということを強調する必要がある。もちろん会社組織に属することが、「働く」ことのすべてではない。
まして、今日では多様な就労形態が存在する。このため、さまざまな「働き方」があって当然である。しかし、重要なことは管理職自身も含めて、会社という組織に属する以上は、組織体での働き方を通して“社会と自分がどのように関わって生きていくのか”という問題意識を持ち続けることだ。
今日では職を得て「働く」ということが、あたかも「就社」と同意語として語られる傾向がある。しかし、一人親方の職人であれ、個人事業主であれ、会社という組織体に属していなくとも、自らの「働き」が社会性を帯びていることに違いはない。つまり、「働く」ということはそれ自体が地域社会や仕事仲間など社会との繋がりである。
仕事とは社会に対して何がしかの価値を提供して初めて成立するものだ。幸いにも会社という組織体は多くのステイクホルダーを事前に備えている。このため、会社組織での働きは、社会に役立つ仕事に必要な技能や能力を磨き高める大いなる「学校」と位置付けることもできる。
自らの働きが社会に役立ってこそ“仕事”としての意味を持つことになる。このため、「社会に役立つ仕事するためには会社勤めである必要がない」という考え方も成立する。一方で「仕事の意味づけ」を自己確認するためには、会社組織での働きが極めて有効に機能する。何故ならば組織体での働きが「共通の目的」と他者との「協働」を通した成果として実感することができるからだ。
会社組織における経営者・上司・先輩、あるいは同僚・後輩、さらには取引先との関係は、組織体に身を置く者にとって何よりの社会経験でもある。自分を中心として上下左右に位置する人びとの意識や行動を見てとることができるからだ。この経験は自己の社会的存在を認識させてくれる。
さて、若手・新人は職場での働きを通して経営者や上司の立ち振る舞いから就労姿勢を俯瞰して観察をする。さらには上司・先輩との接点を通して、自らの立ち位置や観点の妥当性などを検証して就労観を蓄積することになる。とりわけ管理職の言質や行動は部下・後輩に影響を及ぼしながら蓄積されていく。しかし、往々にして若手・新人は職場の管理職や上司の悪しき行動に対して正面から対峙することはない。
このため、若手・新人は仮に職場の管理職や上司の悪しき言質・行動に接したならば、その行為を踏襲するようになるか、無視するようになるかのいずれかだ。いずれの場合にも職場ガバナンスは崩壊することになる。管理職は自らの一挙手一投足が若手・新人から監視されているという自覚を持たなければならない。
| 一覧へ |
![]()