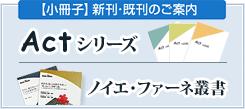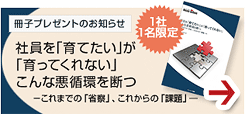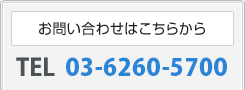人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2014年09月08日号
管理職には部下に仕事を任せる“勇気”が必要
パレートの法則では、“会社の売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している”という事象がよく用いられる。ところが、売上の8割をあげる2割の優秀な人材だけを集めれば、優秀な全員が等しくパフォーマンスを発揮して売上が劇的に変化してするわけではない。この2割の人材の中でパフォーマンスに自然とバラつきが生じ、「優秀に人」と「優秀でない人」に分岐が始まる。
もっとも法則というよりも“何故かしら当たっている”という「経験則」なのだが…。
“よく働く蟻だけを集めても結局は働く蟻と働かない蟻に自然と別れてしまう”という「働き蟻の法則」というのもある。
スポーツの世界でも名選手ばかり集めても必ずしも好成績が残せるわけではない。つまり名選手を集めることと「チーム力」とは別物ということなのだろう。
新卒・中途を問わず採用現場では「優秀な人材」「即戦力人材」の確保が至上命題のように謳われている。とりわけ、新入社員の採用現場ではこの傾向が強い。これは至極当然のことなのだが、はたして採用段階で「優秀」「即戦力」と思しき人材を集中して採用したとしても、不思議とその中で「できる人」と「できない人」の分岐が始まってしまう。すると「優秀な人材」「即戦力」の確保は、所詮「絵に描いた餅」ということになり、現場で仕事を経験させてみなければわからないということになる。
しかし、実際の採用現場では相も変わらず「優秀人材」「即戦力」の確保を求めてやまない。この傾向は人材育成の視点から見た場合には、ある種の「責任放棄」にほかならず、採用と育成を別次元に捉えて「育成コストを抑えられるのではないか」という邪な発想に起因しているのかもしれない。
もちろん、採用にあたっては、自社の特性に見合う要件を備えた人材なのか否か、自社業務の内容をこなしていけるだけの基礎知識や社会人として、健全な発達レベルに達しているのか否かを見極めるのは重要なことだ。
「優秀」と思われる人材集めれば何とかなるだろうと思うのは誤りだ。仮に「優秀」であったとしてもやはり「磨く」行為がなければ、いつまでたっても原石にとどまる。
一般的に“仕事の「できる上司」は、仕事の「できる人」を育てることはできない”といわれている。現実問題として実務遂行能力に長けた上司ほど、部下の仕事が頼りなく見えるものだ。そこで、部下に仕事を任せるよりも自分で仕事を回した方が、効率よく正確にこなすため一定の「着地点」が見えるものだ。しかし、これが落とし穴であることに気付かない。そのため、部下の仕事まで自分で抱え込み、結果的には部下の仕事を取ってしまうことになっている。
さらにいえば、こうした「仕事のできる上司」の下で、部下は上司の指示のみに従うことが習い性になる。そのため、部下は自らの仕事への達成感が持てなくなり、いずれは“上司に指示されたことのみをこなすことが自分の仕事である”と錯覚し、いつまでたっても「できない人」として滞留し始める。
つまり、「仕事のできる上司」のもとでは逆に「仕事のできる部下」は育たないという連鎖のはじまりということになる。
自分の現在の力量と比較して「頼りならない部下」に仕事を任せるのは、できる上司にとっては、不安と逡巡が交差することは間違いない。しかし、この葛藤を乗り越える勇気を持たなければ、いつまでたっても部下は育たたず、いつまでたっても上司自身が次の段階に進むことはできない。
| 一覧へ |
![]()