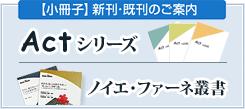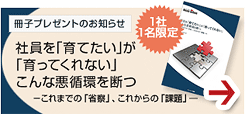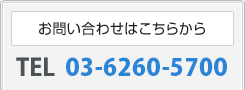人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2012年12月17日号
抽象的に“優秀な人材”を求めては「無いものねだり」に終わる
新卒・中途採用を問わず一般的に採用する側は、「優秀な人材が欲しい」と考える。企業とっては採用コストをかける以上は少しでも「優秀な人材」を求めるのは当然ことである。
ところが、意外と忘れがちなのが抽象的に「優秀さ」を求めるためるあまり、自社の現状にとって必要な人材とは「どのような要件なのか」という定義だ。この「自社にとっての」という前提が重要だ。一般的にどこでも通用するという「優秀人材」が、必ずしも自社の現状や組織体制に沿って必要十分な条件を備えているとは限らないからだ。
特に新卒の採用現場で比較的若い採用担当者が陥りがちなのが、世間一般でいわれている「優秀基準」をそのまま自社に当てはめ、求職者に過重なスペックを求めてしまう傾向だ。企業規模や業種・業態に関わらずに流布している「金太郎飴」的な選考基準が自社の現状を反映した選考になると考えるのは誤りだ。
当然のことながら生まれながらにして万事“有能”な者などは、稀な例外を除いて存在していない。また、会社組織を構成するそれぞれの社員の育ってきた時代背景も異なっている。会社組織は、それぞれ異なる環境や状況の下で育ってきた者達の集合体である。そのため、仕事の適正などは乱暴な言い方だが、会社組織での業務実践を通じて精査されていくものであるという割り切りも必要だ。
採用後も順調に会社の方向性と自らの「働く価値観」を共有することができ、自己の目標設定の下で業務に精通している者もいれば、いつまでたっても同じことを繰り返しながら日常業務を過ごしていることが、「真面目に働くことである」と勘違いしている者もいる。
会社が組織として重視すべきことは、こうした新卒・既存社員を含めて、それぞれ温度差が生じている「働き方」に対する意識差をどのように埋めていくのかということだ。。
そこで今一度「自会社にとって“優秀”な人材」とはどのようなことなのかを整理していくことが必要になってきている。当然、会社の業種・業態、会社の当面の方向によって求められる“優秀”度合いも異なってくる。自社の社員に対して最初から抽象的に“優秀”度を求めるのは、所詮「無いものねだり」だ。
P.F.ドラッカーは「有能さは習得できる」との名言をのこしているが、組織的に取り組まなければならないのは、自社の成長段階に即して、社員に求める技能や役割意識などの必要な能力を定め、計画的に“優秀さ”習得に向けた機会(=教育の場)を提供していく姿勢だ。
もちろん、自ら『学ぶ』意識の無い者に対して、企業は組織としての責任を負いかねることも確かだ。
| 一覧へ |
![]()